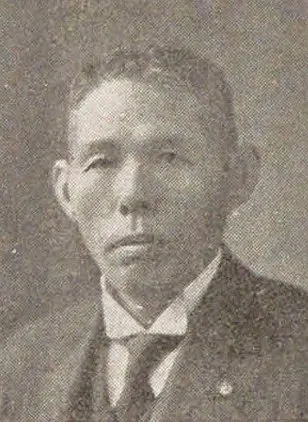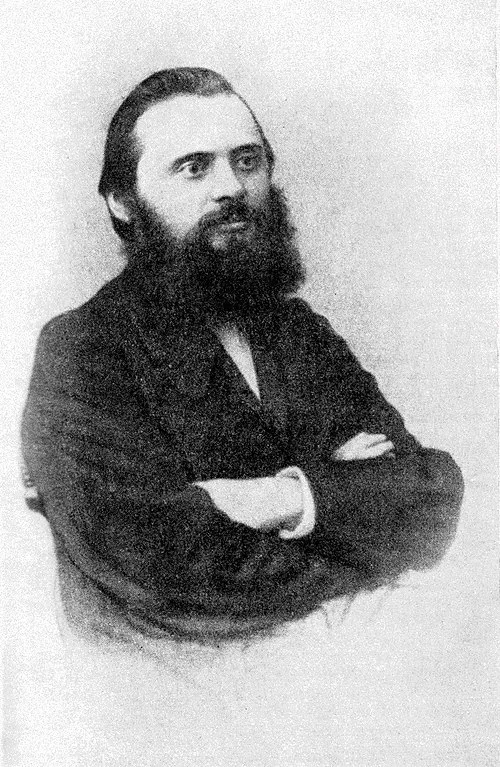名前: 三遊亭圓盛
職業: 落語家
生年: 1869年
没年: 不詳
年 三遊亭圓盛落語家 没年不詳
ある冬の日年の日本まだ明治時代の足音が聞こえるこの時期東京の小さな町に一人の男が生まれたその名は三遊亭圓盛彼は落語家として名を馳せる運命を秘めていたしかしその道は決して平坦ではなく数の試練と困難が待ち受けていた
幼少期圓盛は家庭の経済状況が厳しく学校に通うこともままならなかったそれでも彼は言葉遊びや物語に魅了され自ら進んで落語を学ぶことに決めたその背景にはおそらく彼自身が抱えていた孤独感や社会との断絶感があったのかもしれない
成人する頃にはすでに町内では話し上手として知られるようになっていたそこで彼は自身の才能をより多くの人に知ってもらうために舞台へと足を踏み入れることになるしかしそれにもかかわらず最初から注目されたわけではなく多くの時間と努力を要した
特筆すべき出来事として彼が参加したある地方のお祭りで披露した演目が観客から絶賛されたことで一躍有名になったというこの成功によって東京でも活動する機会を得ることになるしかしこの成功には皮肉な側面もあり多くの嫉妬や敵意も呼び起こしてしまった
三遊亭圓盛はその後多くの弟子を持ちその教え子たちは後世まで続く落語界へと道を広げていった歴史家たちはこう語る圓盛なしでは日本の落語文化は現在ほど豊かなものにはならなかっただろう
しかしながら一方で彼自身も多忙な日によって疲弊し自身の日常生活とのバランスを保つことが難しかったようだおそらくこの精神的負担こそが後年彼への影響となる原因だったと分析する専門家もいる
そうこうしているうちに大正時代突入と共に日本全体で新しい文化潮流が訪れるしかしそれにもかかわらず圓盛はいまだ古典的なスタイルに固執し続け新しい表現方法への適応には苦労したこの選択肢こそが功罪両面あったとも言えるだろう実際新しい風潮への対応能力不足こそ本当に悩ませた点だったとファンたちからも聞かれる意見である
そして運命の日晩年その姿勢ゆえに観客から忘れ去られてしまい孤独死死因について詳細は不明だがその影響力と作品群だけは永遠となり続ける皮肉にも生前人気だった若手落語家たちとは対照的に急速にその名声は薄れていき結局最後まで注目されずという評価さえ残された
今日でも三遊亭圓盛という名前を見る機会がありますその影響力から生まれた多くのお話や演目は日本文化として息づいており新世代によって再解釈され続けているそしてなんと今なお古典という立場ながら新作として舞台化されることもしばしば
こうして振り返れば不遇な晩年とは裏腹にもその遺産はいまだ色褪せず多く人によって大切に扱われているそれぞれ異なる形で評価され続ける中歴史とは常に勝者だけによって書かれるわけではないという事実について考えさせてもらえる存在なのである