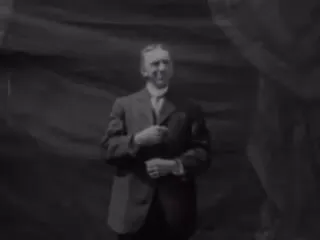ゴールデンウィークの意味と重要性
ゴールデンウィークは日本の最も重要な連休の一つであり毎年月末から月初めにかけて行われるこの時期日本人は通常数日間の休日を利用して旅行や帰省家族との時間を楽しむ実際国民の祝日が続くためこの期間は多くの人にとって特別な意味を持つ
ゴールデンウィークは昭和年年に制定されたこどもの日やみどりの日を含む祝日の連続によって形作られたその後天皇誕生日などが加わり現在では日本人にとって最も待ち望まれる長期休暇となったこの時期には観光地が賑わい人が普段できないさまざまなアクティビティを楽しむことからその重要性は計り知れない
喜びの波休日と再会の調べ
その瞬間誰もが息をのんだ街には色とりどりの提灯や飾り付けが施され人は心躍る旅への準備に忙しい赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った祭りの日一家団欒で囲む食卓にはお母さんが作った郷土料理が並びその美味しさは心まで温める
夜明け前繁忙な道への旅路
早朝小雨交じりの日曜日車窓から見える山は青みを増し大自然へ向かう道筋であることを教えてくれる日本各地へ向かう渋滞する道路は一年中待ちわびた連休という合図だその風景には伝説的な桜並木も映え人はその美しさに目を奪われる
この時期多くの場合旅行をテーマとして計画され多種多様な観光地やレジャー施設で賑わう温泉遊園地歴史的遺産の三拍子揃った目的地こそ日本独特のおもてなし文化を体現しているしかしその旅路には必ず何らかの思い出やエピソードが伴うものだ
子供たちの思い出帳
小さな手で握られた色鉛筆そのノートには大好きなおじいちゃんおばあちゃんとの思い出やお友達との冒険話それぞれ一枚一枚描かれている山登り川遊びさらには楽しかったバーベキュー大会までそれらすべてがこの時期ならではだからこそ価値あるものとして刻まれている
親子三代
おじいちゃんおばあちゃんまた夏になったら遊びに来てね