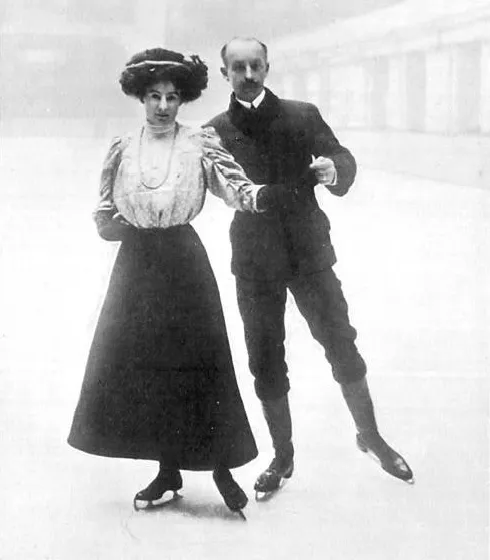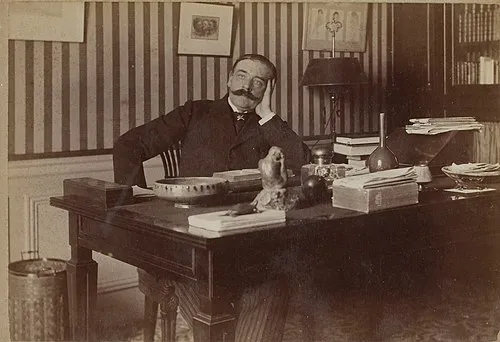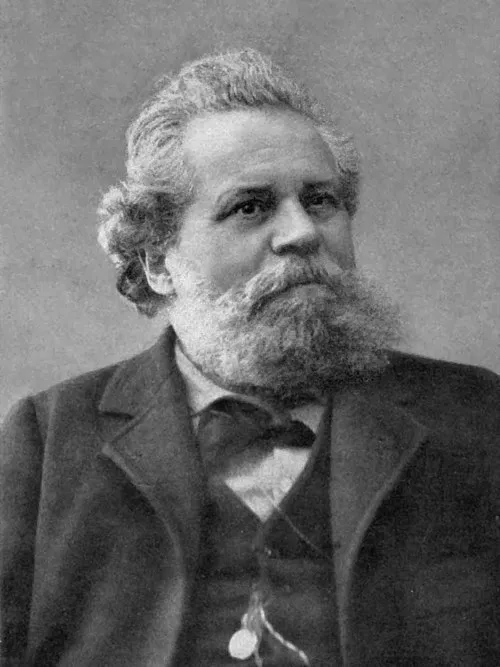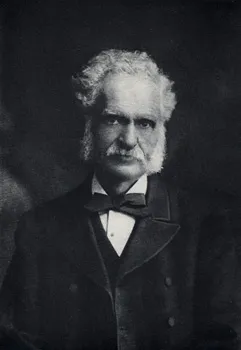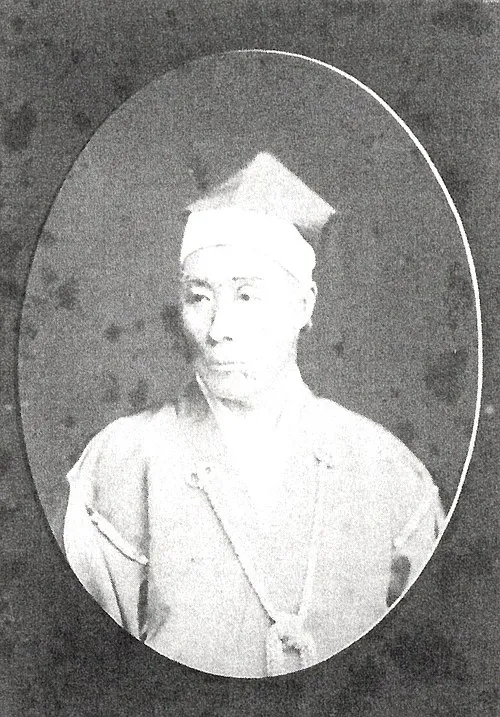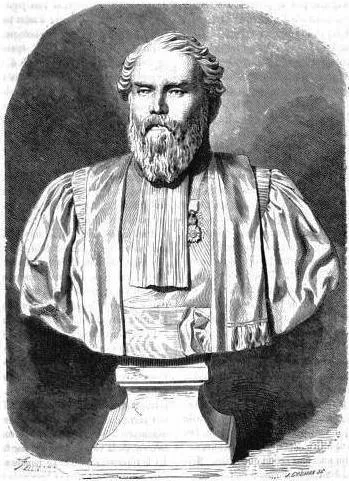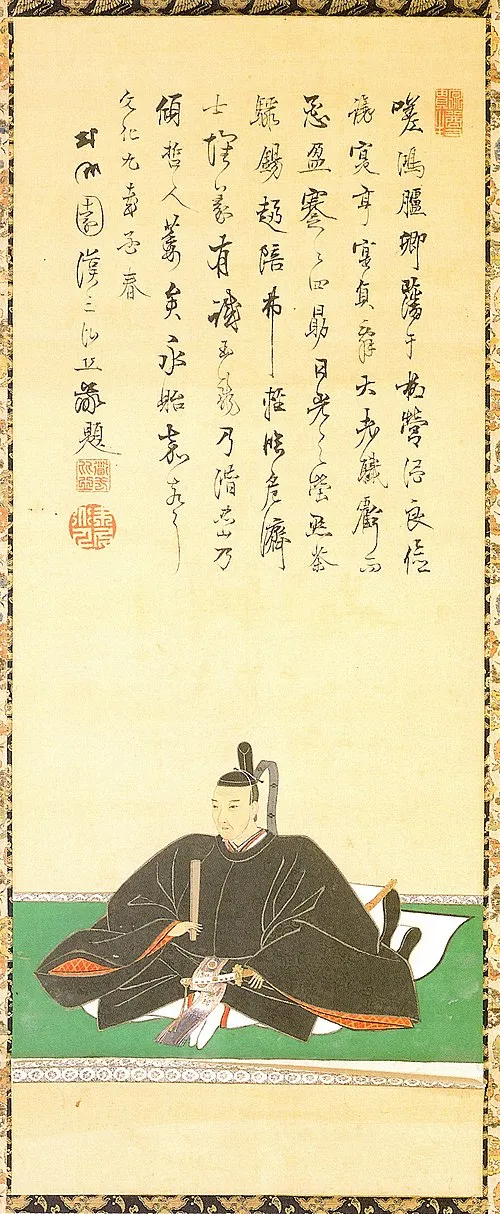生年月日: 1911年
死亡年: 1951年
職業: 作曲家
国籍: 日本
年 尾高尚忠作曲家 年
尾高尚忠は年に日本の音楽界の中心地とも言える東京で生まれた彼の幼少期は戦争と混乱に彩られた時代だったがその影響を受けることなく音楽に対する情熱は次第に彼を導くこととなったしかし家族から受け継いだ厳格な教育が彼の創作意欲を抑え込もうとしたため若き日の尾高は内なる葛藤を抱えることとなった
学生時代にはバイオリンやピアノといった楽器に触れる機会が多かった特にクラシック音楽への傾倒は強くそれが後の彼の作曲スタイルにも大きな影響を与えたと言われているその一方でジャズやポピュラー音楽にも心惹かれそれらも取り入れた独自の作品づくりへとつながっていく皮肉なことにこの多様性こそが後年の評価につながる要因となるのであった
大学では音楽理論や作曲について深く学び自身のスタイルを模索する日が続いたそして年代初頭日本経済が復興しつつある中で多くの新しい文化的動きも芽生えていたこのような背景下で尾高は年自身初となるオーケストラ作品交響曲第番を発表するそれにもかかわらずこの作品は当初大衆にはあまり理解されず苦難の日も味わったしかしその一方で一部から高い評価を得ることになりその後もさまざまな公演で演奏され続ける
尾高尚忠が名声を得ていく過程では多くの人との出会いや影響も重要だった特に当時著名だった指揮者とのコラボレーションによって彼自身の作風にも変化が訪れるおそらくこの時期日本国内外から集まってきた様なアイデアや感性との交わりこそが彼をさらに成長させる土壌となったのであろうしかしそれでもなお自身の日常生活では孤独感や不安感とも闘っていたというそうした複雑さこそが人間として魅力的な部分でもあった
その後も数多くの名作を生み出し日本オペラの分野でも知られる存在へと成長していった皮肉なことに才能ある作曲家として活動している間にも世間から評価されない苦悩の日は続いたその中でも彼自身大切にしていた信念音楽とは心そのものと言う考え方だけは失うことなく持ち続けていたという
晩年になると日本交響楽団などとの協力関係によってますますその名声はいっそう強固になり多数の演奏会で取り上げられるようになるその頃には既に歳近かったもののおそらく尾高自身には老齢など感じさせない情熱的な姿勢だったと言われているしかしそれにもかかわらず健康問題によって活動制限が出始めたころには不安感や焦燥感も募り始めていた
そして年代初頭その業績ゆえか注目され始めたいっぽうで新しい世代への引継ぎや再評価への期待感も増していた矢先でした皮肉なことだがこのタイミングで起こった急激な体調悪化によって最終的には年月日に静かにその幕を下ろす結果になりましたこの出来事によって日本国内外問わず多方面から追悼・評価されたことで改めて音楽界への貢献度合いや影響力について議論されるようになります
今なお多数存在する録音資料や公演記録などから残された足跡を見る限りでは彼自身だけではなく日本全体として非常に大きなインパクト残した偉大なる作曲家として記憶されていますそして最近新たなる世代によるカバー作品等活躍する姿を見ると伝承という形で永遠不滅とも思える存在になっていますこれぞまさしく現代社会との繋ぐ役割なのです