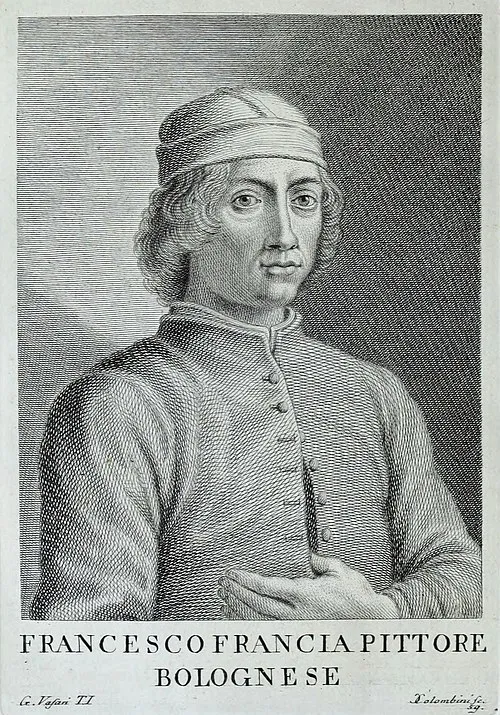生年月日: 1828年(文政10年11月19日)
名前: 小林一茶
職業: 俳人
生年: 1763年
年文政年月日 小林一茶俳人 年
年月日深い秋の空気が漂う中日本の俳句界に一つの大きな影が落ちることとなったこの日小林一茶が静かにその生涯を終えたしかし一茶の人生は単なる年数で語り尽くすにはあまりにも豊かで彼自身の詩と同じように多層的だった
年長野県の小さな村で生まれた一茶は幼少期から自然や人とのふれあいを大切にしていた彼は言葉に宿る力を早くから理解しその才能は周囲を驚かせていた彼自身俳句こそが私の命と語っていたと言われるしかしそれにもかかわらず一茶の人生には常に逆境が伴った
若い頃一茶は家計を助けるために農業を手伝わねばならずその生活は厳しいものであったおそらくその困難な環境こそが彼の詩的感性を磨き上げた要因だったとも考えられる皮肉なことに貧困や苦しみは彼の詩作りには欠かせない材料となり多くの名作へと昇華していった
成人すると一茶は江戸へと出て行くことになったしかしこの移動もまた運命的な出来事だった江戸で出会った多くの文人や仲間たちとの交流によって一茶は自らのスタイルを確立していくそれでもなお彼には多くの試練が待ち受けていたその中でも特筆すべきなのは家族との別れだ一生涯愛した妻や子供たちとの悲しい別れそれらは後まで彼を悩ませ続けた
しかしそれにもかかわらず一茶は創作活動から逃げることなく自分自身と向き合い続けたそして年代になると特有なユーモアと鋭い観察力によって人の日常生活や自然現象への愛情溢れる視点から新しい形態俳句を書き上げるようになっていた雪と春をテーマにした作品群など多様性ある作品群で日本文学史上不朽なる地位を確立するその過程ではおそらく失われたものへの強烈な思慕もありそれが作品全体として深みとなって表れているようだ
小林一茶という名前が全国区として知られるようになった今その影響力はいまだ色褪せてはいない近年ではこれぞ現代俳句という新しいスタイルも登場し多様化する日本文学界へ新風を吹き込んでいるこの現象についてある評論家はいこう評している一茶こそ日本俳句文化再生への道標なのだとその証拠として挙げられる多数の模倣者やファンその全てが時代を超えて共鳴し合う瞬間こそ本当のお礼だと思う
死後年以上経過した今でも小林一茶という存在感溢れる人物その言葉や精神性・そして作品これは常に我の日常生活へ浸透しているそして何よりこの無二なるクリエイターとして残した数のお宝とも言える句達記録によれば春よ来いという一句には特別な意味合いも含まれていて望み続ける心を読者へ投げ掛けていると言えるそれゆえ本当に皮肉なのだ今日でもこの一句からインスパイアされた創作者達未来世代への希望とは何かそれこそまさしく小林一茶流
一見シンプルながら奥深さ故意識されない微細さ美味しそうで目にも楽しい四季折のお菓子これほど幅広い魅力持つ人物他者との違いや個性的表現主張する価値観この独自性ゆえ歴史的俳人でもあり続け決して古びない存在感未来永劫人によって語り継がれ恵み与えてゆくだろう