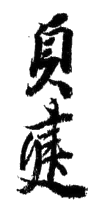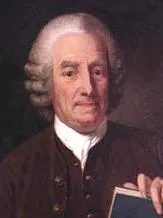生年月日: 1718年(享保2年12月28日)
死年月日: 1784年
職業: 旗本
研究分野: 有職故実
年享保年月日 伊勢貞丈旗本有職故実研究家 年
年のある寒い日伊勢貞丈は静かな家族のもとに生まれた彼は旗本としての血を引きその家庭環境は彼に多くの教養を与えたしかし幼少期から目立つ存在ではなかった彼が自身の道を切り開くことになるとは誰が想像しただろうか成長するにつれて伊勢は有職故実に対する興味を抱くようになったこの分野への情熱が彼を駆り立てさまざまな書物や文献に没頭させることになるそれにもかかわらず当時の日本社会では有職故実について学ぶこと自体が容易ではなく多くの人が無視していたしかしそんな逆境にも関わらず伊勢は自身の学問を深めるために努力を惜しまなかった若い頃には多くの著名な師匠から学びその知識と理解力は徐に高まり続けたその結果有職故実研究家として名声を得ることになった皮肉なことにこの時代日本社会は変革期にあり新しい思想や価値観が台頭していたそれでもなお古き良き伝統や文化への敬意と理解を重んじる姿勢こそが伊勢貞丈の真骨頂であったおそらく彼自身もこの二つの世界新旧が交錯する中で自身の役割について葛藤していたことであろう年には自ら集めた資料や研究成果を元に有職故実考という著作を書いたこの作品には日本古来から受け継がれてきた儀式や風習について詳述されており多くの後進たちへの道しるべとなった記者会見で彼はこう認めた私たち日本人には自分たち自身について知る権利がありますそれこそが我文化人として果たすべき責任なのです年代までにはその名声はいよいよ高まり多くの記事や書籍でも取り上げられるようになっていたしかしそれにも関わらず世間的な栄光とは裏腹に晩年になっても孤独感から逃れることのできない人生だったその背景には一緒に学び合える仲間との出会いや絆が少ないという厳しい現実もあったと思われる年月日それまで数十年間続けてきた研究活動の日が終わりを迎えようとしていたそしてこの日多くのおそれと共感で囲まれながら静かに息を引き取ったあるファンは街頭インタビューでこう語った今でも伊勢貞丈によって示された道筋があります我現代人もまたそれによって刺激されます今日では有職故実という言葉自体あまり耳馴染みないものとなっているしかしながらそれゆえこそ彼の日努力した足跡や業績を見ることで新しい視点とともにつながり合える何か存在し続けていると言えるだろう皮肉にも人間味溢れる不完全さゆえ生じるこの繋がりこそ優れた歴史的研究者と呼ばれる所以なのだ