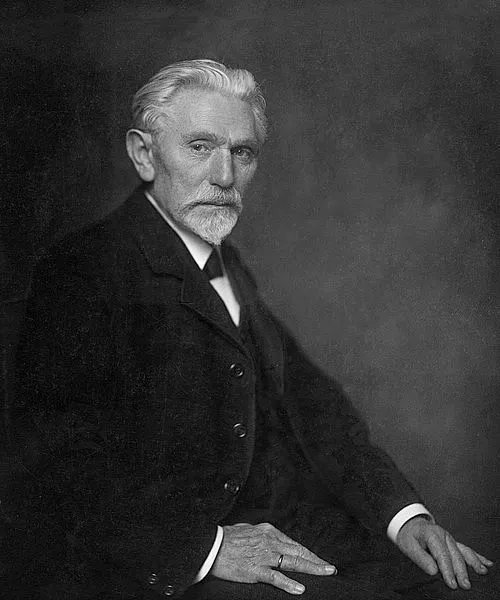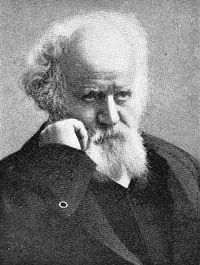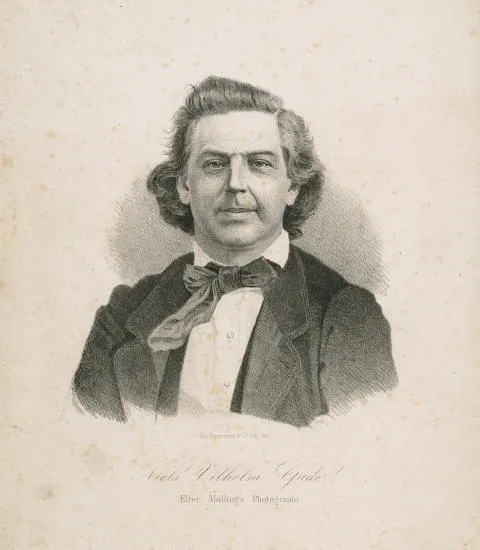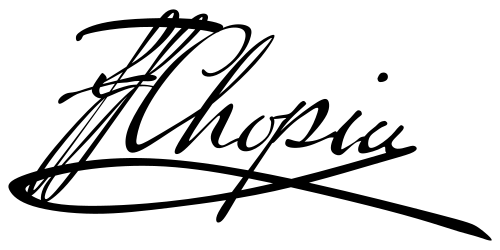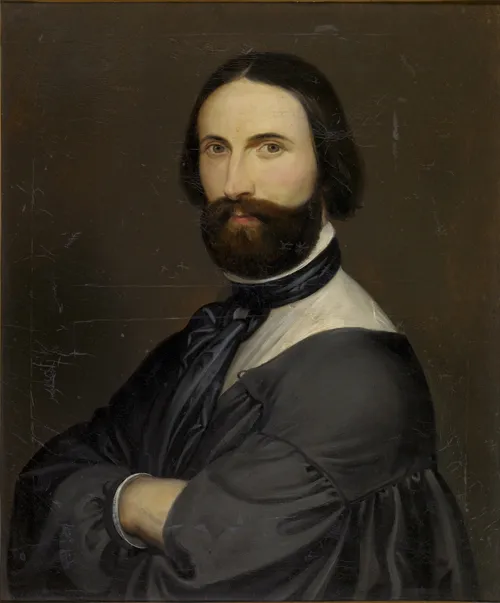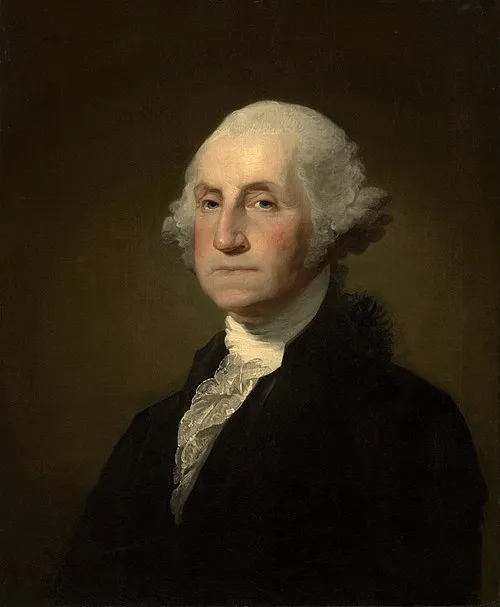生年月日: 1846年
名前: エラ・アダイェフスカヤ
職業: ピアニスト、作曲家、民族音楽学研究家
没年: 1926年
エラ・アダイェフスカヤ 音楽の橋を架けた女性
年ロシアの小さな町で生まれたエラ・アダイェフスカヤは音楽に対する深い情熱と才能を持つ子供として知られていた彼女が初めてピアノの鍵盤に触れた瞬間それはまるで彼女の運命が決まったかのようだった家庭では音楽が溢れ彼女はいつしかその旋律に包まれる日を送っていた
若き日のエラは地元の音楽学校で厳格な訓練を受けることになりその中で多様な音楽スタイルに触れるしかしその道は平坦ではなく家族や友人からの期待に応えようとするプレッシャーも感じていたそれにもかかわらず彼女は独自のスタイルを築き上げていく特に自身の民族的背景から影響を受けたメロディーやリズムが彼女の作品には色濃く表れていた
ピアニストとして成長する一方でエラは作曲にも挑戦した最初期には伝統的なクラシック音楽に則った作品を書いていたが次第に自身のアイデンティティを反映した民族的要素を取り入れるようになるその結果生まれた作品群には聴く者すべてが共鳴できる深い感情が宿っており多くの人を魅了したしかし皮肉なことにこの新しいスタイルには賛否も分かれ多くの批評家から反発されることもあった
民族音楽学への探求
時代が進むにつれて彼女は単なる演奏者や作曲家以上となっていったエラは自国だけでなく周辺諸国からも民俗音楽について学ぶため旅立ちその土地固有のメロディーやリズムへの興味を深めたこの頃から彼女自身の研究活動が始まり民族音楽学という新しい分野への扉を開いていく
ある報告書によれば地方で聞こえてきた旋律こそ本当の文化遺産だと語ったことでも知られているこの言葉にはおそらく当時急速に西洋化している社会への強い危機感があったと思われるそのため彼女はいわゆる本物の文化とは何かという問いへと向き合うことになり多くの場合それらすべてを書くことで記録し続けていたこれは後世への貴重な資料となりそれ以降多く研究者によって評価されるきっかけともなった
晩年と遺産
年歳という長寿を全うしたエラ・アダイェフスカヤしかしながらその死後も彼女が築き上げた道筋と影響力は決して薄れるものではなく多く後進へと受け継がれていった皮肉にも一部では忘れ去られし者と見做されながらも実際にはその足跡こそ現代でも大切にされ続けている例えば今日でも各地で行われるフォークフェスティバルではエラによって紹介された民謡や作曲された旋律を見ることができ多様性ある文化として再評価され続けている
現代とのつながり
の名声はいまだ健在だ一部地域ではコンサートホールが建設されその名もエラ・アダイェフスカヤホールと命名されたまた近年この偉大なる女性ミュージシャンについて描かれたドキュメンタリー映画まで制作されたそれによってさらに多く人へ を届けようという試みなのだろうそしてこの世代交代にも関わらずまたそこから派生する問題世代さえその独特さやパッションについて熱心に語り合う姿を見ると本当に驚きを禁じ得ない
結局時間とは流れてしまえば一瞬しかしその中でも確かな影響力へ繋げ得られる意義とは何かそこで提示されたひとつとして真実は常に私達の日常生活中どこでもあるものなのだと思わず考えさせられるそしてこの先どんな形になろうともこれまで積み重ねられて来たいわゆる社会的意味含む物語達として我自身運命関係構築し共存して行こうそれこそ必須要件なのでしょうね