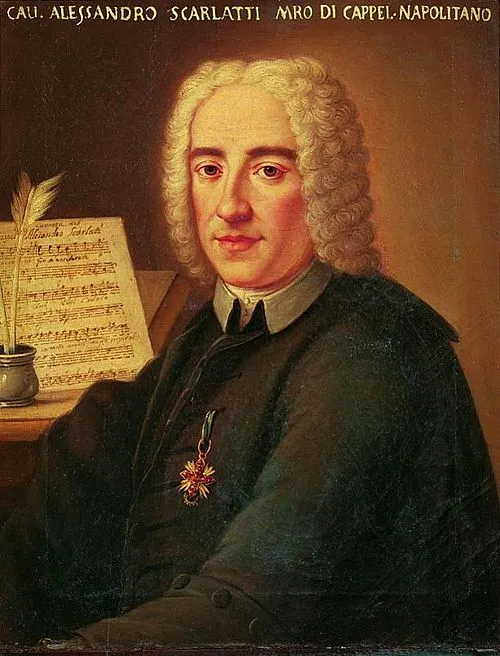生年月日: 1661年4月4日(万治4年)
職業: 俳諧師
没年: 1738年
名前: 上島鬼貫
上島鬼貫俳諧の詩人とその影響
年江戸時代の日本に一人の男が誕生した彼の名は上島鬼貫彼が生まれた時まだ国は平和な時代を迎えたばかりであったが戦国時代の名残が心に色濃く残っていたしかし鬼貫はその混沌とした世相から脱却し言葉という武器を使って新しい文化を築こうと決意する
若き日の鬼貫は多くの詩人や文人たちに囲まれて成長した特に俳諧という文学ジャンルに魅了され自らも詩作に励んだそれにもかかわらず彼はただ単に模倣するだけではなく自身の独自性を追求したその結果として多くの弟子たちが彼について来るようになった
数の挑戦と栄光
年代には既に名声を博していた鬼貫だったがそれでも多くの苦悩と挑戦が待ち受けていたある日有名な藩主との間で意見対立が起こりその結果として一時的な失脚を余儀なくされたしかしそれにもかかわらず彼は諦めることなく新しい作品を書き続けていったこの執念こそが後世まで語り継がれる理由となった
また一方で彼には魅力的なライバルも存在していた例えば高浜虚子との関係性だ二人とも互いに刺激し合うことでおそらくより高いレベルへと自分自身を引き上げていったのであろう皮肉なことにこの競争関係こそが日本文学界全体へと新風を吹き込む要因となった
芸術家としての日
鬼貫の日常生活には多様性があふれていた自然や人との出会いからインスピレーションを得る一方でその感情や景観を言葉で巧みに表現したまた俳句だけではなくその背景となるエッセイや短編小説も手掛け多岐にわたる才能で知られた
もちろんこの過程では成功だけでなく失敗も伴っただろうしかしながら失敗は成功の母と言われるようにこれまで得てきた経験や教訓によって進化し続けたそれゆえ多くの場合人は彼への期待感からも大きな影響力を感じ取っていた
死後も語り継ぐ存在
年歳という年齢でこの世を去った上島鬼貫しかしながら彼の影響力はその死によって消えることなく日本文学界には今なおその足跡を見ることができる静かな夜の中で行われた様な交流や対話それ自体がおそらく永遠なるものなのである
実際その後何百年もの間日本全国各地では鬼貫と呼ばれる作品群への再評価や研究活動も続いているこの現象こそ皮肉とも言える命尽き果ててもなお生き続ける魂がそこには存在しているからだそして現在でも多くのファンや学者によって引き継ぎ新しい解釈によって再評価され続けているのである
結論として現代への影響
法人など文化活動団体によって行われている俳句ワークショップはこの偉大なる詩人のおかげとも言えるその精神は今でも我の日常生活にも息づいており人間同士・自然との結びつきを再認識させているまた不完全さや美しさについて考えさせる機会ともなるそして更なる未来へ向けてもこの流れは途切れること無く受け継がれていくだろう