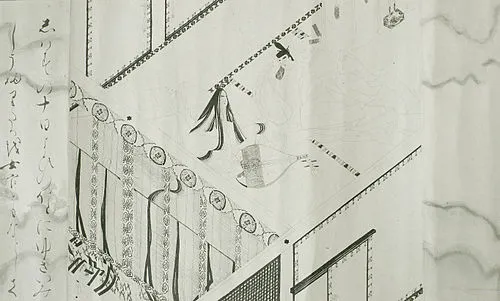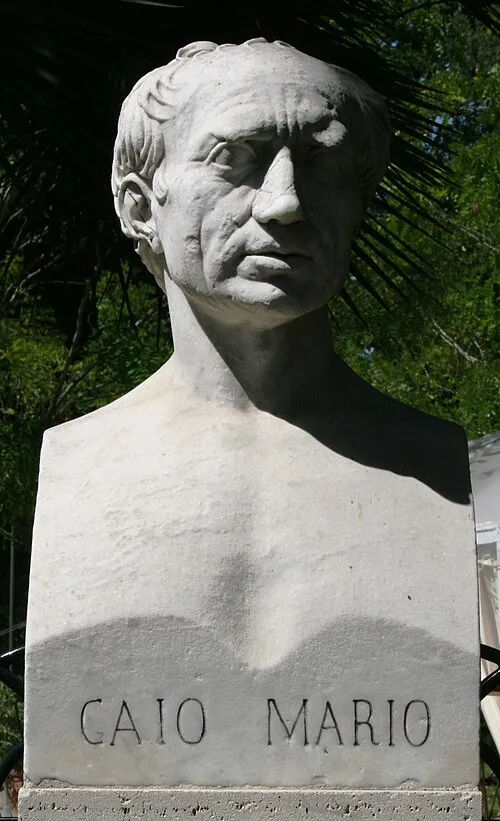生年: 1721年
没年: 1765年(明和元年12月22日)
役職: 一橋徳川家初代当主
氏名: 徳川宗尹
年明和元年月日 徳川宗尹一橋徳川家初代当主 年
年冬の寒さが漂う中一橋徳川家の初代当主徳川宗尹がその人生を歩み始めたこの年は江戸幕府の時代における大きな転換期でもあり彼がどのようにしてその波乱万丈な歴史の一部となっていったかは興味深い物語である宗尹は年に生まれたが若き日を経て家族とともに権力の中心から離れた場所で成長したそのためかおそらく彼には外界への強い好奇心が芽生えていたに違いない
彼の人生は一見平穏無事に見えるものであったしかしそれにもかかわらず幕末期への緊張感は高まっており権力闘争や内紛と向き合うことになった実際彼が成長するにつれて一橋家という名門家系が日本史上どれほど重要であるかを理解し始めたことでしょう皮肉なことにその地位ゆえに多くの期待とプレッシャーを背負うことになったのだ
若い頃から政治的な才覚を発揮した宗尹だったがその道程は容易ではなかった特に年には自身や一橋家への期待が膨らんだ一方で多くの対立者も存在していたそれでもなお人間関係という複雑怪奇なネットワークを巧みに操りながら進む姿勢は一種のマキャベリズムとも言えるものだったその一方で人から信頼されるためには誠実さも必要だということを忘れるわけにはいかなかったのである
記録によればこの時期宗尹は近隣諸国との外交交渉にも積極的だったと言われているしかしこの外交活動はいわば二面性を持つものでありその裏側では同じ日本国内でも権力抗争が繰り広げられていた政治的才能だけではなく人間関係スキルや心理戦にも秀でていた点について多くの人から称賛される理由だった
また有名なのは彼自身による武士として生きる以上公平無私であれという信念だそれにもかかわらずこの信念と現実とのギャップには苦しんだこともあったようだ正義と利益の狭間で揺れる日常生活これこそが当時生き抜いていた武士たちの日常だったそしてこの点こそ徳川宗尹自身も深く考えざるを得ない運命となってしまった
年代初頭になると日本全体では欧米列強との接触や影響力拡大について議論され始めそれによって将軍職や大名家へさらなる変化を求める声も高まり続けていた一方的な従来型体制から新しい何かへ転換する必要性この圧力こそ未曾有とも言える歴史的背景となり得た議論とは裏腹にその矢面となってしまう立場とは非常に厳しいものだったと言える
しかしながらそれでも徳川宗尹という人物自身の日は明暗様だった当時著名だった文化人との交流や自身による書物作成など多岐にわたり活動していたまたこの国柄という概念について考察し新しい価値観形成へ寄与した部分でも評価されているこの流行文化への適応能力こそ日本社会全体として前進するためには不可欠なのかもしれない
年代になると更なる動乱期へ突入してしまうそれにも関わらず生涯通じて静謐を保ち続けたいという願望これこそ古今東西問わず多くの指導者層共通した思考法とも言えるしかしこの静謐さとは決して無意味ではなく自身及び自分以外への配慮と思いやりから成り立つ美徳でもあったと言えるただ単なる冷淡さとして解釈された場合不幸な結果しか招かなかった可能性すら秘めていただろう
そして年大老職任命後しばしば語られる出来事それこそ大政奉還への流れとなり得た出来事この瞬間そのものだけ見ても短絡的評価しか下せない部分ではある全般的状況により影響された結論だからこそ遺族世代まで及ぶ展開として語ればそれぞれ別次元のお話になろうまた定説化された評価・批判とかにも目を向けつつ理解した方がお互いフレキシブルなのだから
年代以降再び全国単位再編結束運動改革の兆候ある中果敢なる挑戦姿勢崩す事無く頑固さ保ち続けて来ましたでも果敢故ゆえ相対顕現先頭登場人物意識持ちなさいよ本当に色んな問題提起経過辿って行けば日本社会変容ただただ停滞待つのみになっちゃいますよ
皮肉なことだが最終的には年あたりまで存命但し辺り不在故ハンデ背負いつつ亡命生活送ったみたいですね最終回帰結局年死去歳超えて大台乗せ皆色んな想像巡りますでしょう