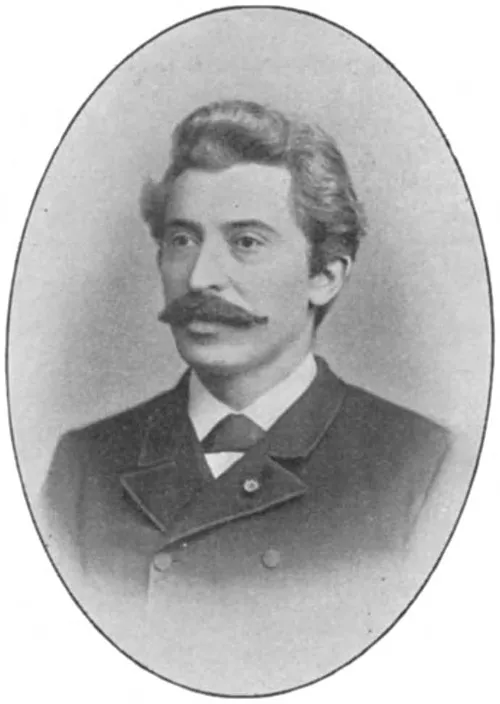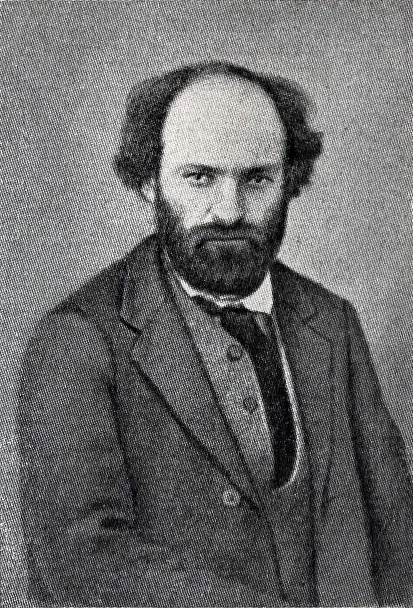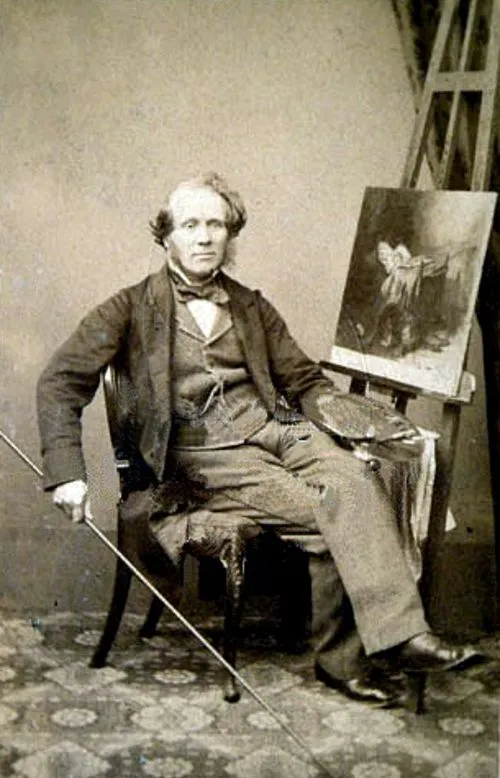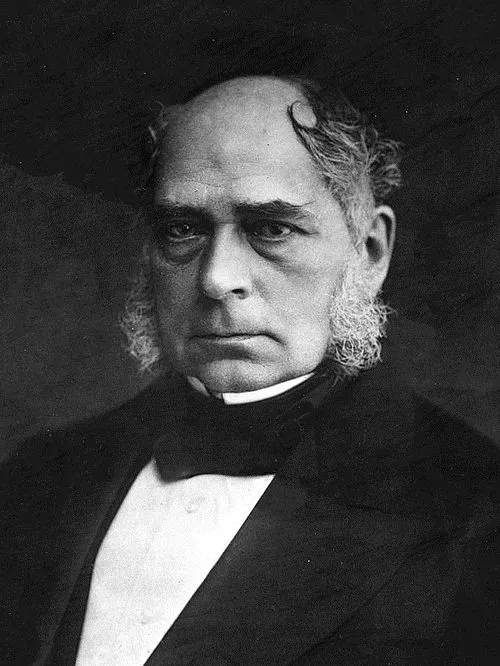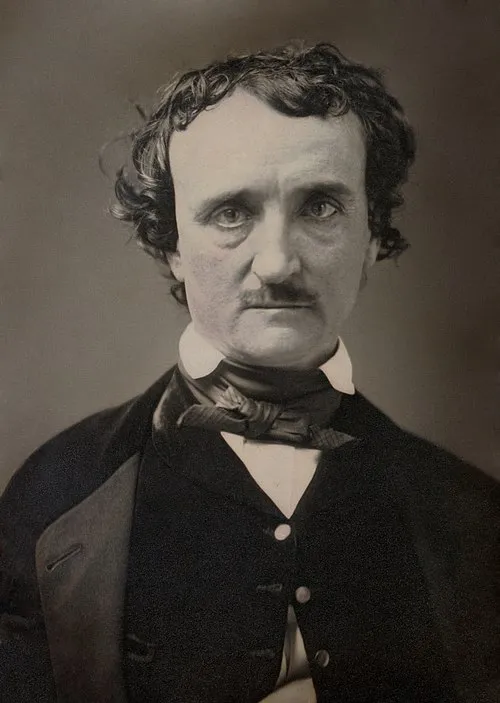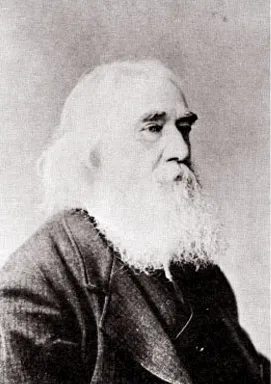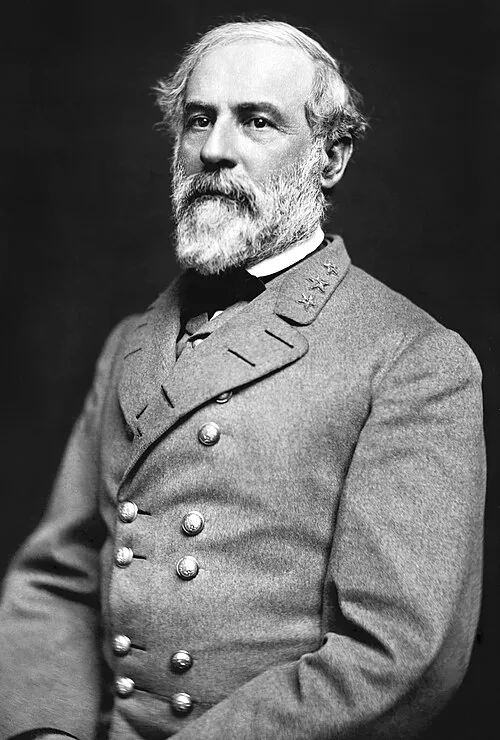生年月日: 1864年(文久3年12月11日)
氏名: 小山作之助
職業: 作曲家、教育者
没年: 1927年
小山作之助音楽と教育の架け橋
年文久年の月日日本のある静かな村に音楽の未来を担う子どもが生まれたその名は小山作之助周囲は彼の誕生を祝ったが誰もが彼が後に日本の音楽界に与える影響を予想することはできなかった
幼少期小山は自然と音楽に親しんだ父親から教わった琴や笛を通じて彼の心にはメロディーへの情熱が芽生えていったしかしそれにもかかわらず当時の教育システムでは伝統的な日本音楽ばかりが重視されていたため西洋音楽との出会いは遥か遠い夢だった
それから数年後明治維新という大きな変革期が訪れるこの時期西洋文化への関心が高まり多くの人が新しい知識や技術を求めるようになった小山もまたその流れに乗り遅れることなく西洋音楽への探究心を抱くようになるおそらく彼自身も自分の才能と情熱を活かす道を見つけたいと思っていたのであろう
若干歳で上京した小山は東京音楽学校現・東京芸術大学で学び始めるそしてここで彼は西洋クラシック音楽だけでなく日本伝統音楽との融合について深く考え始めるしかしこの時代日本ではまだ西洋文化と伝統文化との対立も見られていたため小山には多くの試練が待ち受けていた
成功と挫折教育者としての道
小山作之助は卒業後教育者として活動することになり多くの学生たちに影響を与えたその授業スタイルや教材には特異性と創造性が溢れており多くの場合生徒たちはただ教科書通りに学ぶだけではなく自分自身で考える力を養うことができたそれにもかかわらず一部では伝統文化への挑戦として批判されることもあった
その中でも特筆すべきなのは日本初となるオペラ夕顔の作曲だこの作品は西洋オペラ形式に基づいているものの日本的な題材と旋律で彩られている当初多くの人から期待されながらも本物のオペラとは認められないという冷たい反応も受けたしかし皮肉なことにこの作品こそ小山自身だけでなく新しい日本音楽界全体への道筋となったのである
晩年影響力ある存在として
年小山作之助はいよいよその人生幕引きを迎えるしかしその死によって彼自身だけではなく多くのみんなへ与え続けた影響力までも消えてしまうわけではなかった歴史家たちはこう語っている小山なしには日本近代音楽史は語れないと今なお多様性あふれる日本ミュージックシーンには小山作之助によって築かれた基盤があります
現代との繋がり
今日でも小山作之助によって提唱されたアイデアやスタイルを見る機会があります一部アーティストたちは和の要素を取り入れながら新しいジャンルへ挑戦しているそれにも関わらず一方では本当にこれこそ日本だと主張する保守的な意見も存在し続けていますこのように時代背景や価値観によって評価され続けることでしょう
最後に
何より重要なのは自分自身を表現することでありそれこそ真実なる芸術だ 小山作之助生前この言葉とも呼べる信念から多大なるインスピレーションを受けました後世へ残したレガシーそれこそ永遠なる旋律ですそしてそのメロディーはいまだ未来へ向かっています 死から年経過した今なお多くの日常生活やイベントなどでもその精神性は色濃く残っています