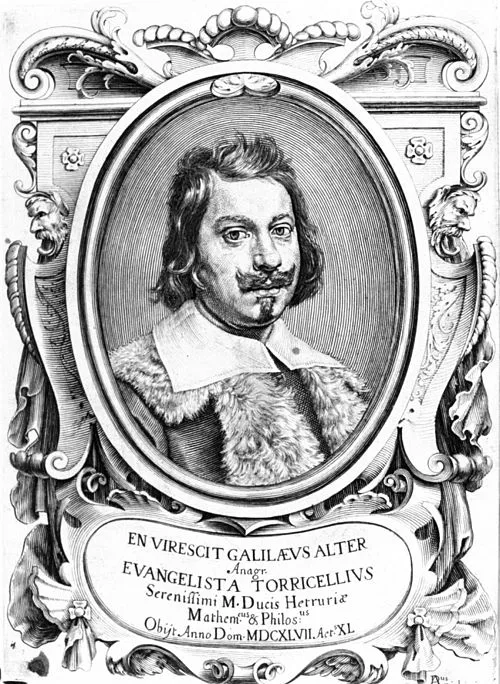生年月日: 1814年
名前: ミハイル・レールモントフ
職業: 詩人、小説家
死亡年: 1841年
ミハイル・レールモントフ ロシア文学の光と影
年ロシア帝国の美しい大地に誕生したミハイル・レールモントフは後に詩人や小説家として名を馳せることとなるがその道のりは平坦ではなかった彼は裕福な家族に生まれ育ち幼少期からその才能を開花させたものの内面的な葛藤と社会との摩擦が彼の心を常に揺さぶった
若き日に彼が直面した運命はまさに皮肉であった父親を早くに失い母親と共に祖母のもとで育てられることになったがその環境は彼に豊かな創造力を与えたしかしそれにもかかわらず家庭内で感じる孤独感や疎外感はいつも彼につきまとっていたそしてその孤独感こそが後年の作品群にも色濃く反映されることになる
年レールモントフはペテルブルク大学へ入学するこの時期多くの文人や知識人との出会いがあったしかしそれにもかかわらずこの華やかな都市生活には多くの不満も抱いていた彼は当時流行していたロマン主義文学から多大な影響を受け自身でも詩を書き始めた特筆すべきことにはこの頃書かれた死者への手紙がありおそらくこの作品がレールモントフ自身の存在意義について深く考える契機となったのであろう
年その名声は一気に高まり英雄という言葉が彼の日常語となっていたしかしながら一方で当時著名な詩人プーシキンとのトラブルによって社会的地位も脅かされたそしてそれこそが皮肉な運命だったプーシキンとの対立によって起こった決闘ではプーシキン自身が命を落としてしまいそれ以降レールモントフには多くの非難と疑念が寄せられることとなったこの事件によって歴史家たちはこう語っているレールモントフという才気溢れる青年も一瞬で悪役になり果てた
決闘後彼はカフカース地方へ追放されるこの地への流刑生活こそがレールモントフ文学の重要な要素となり多数の優れた詩作および小説執筆につながるそれにもかかわらず孤独と失意の日には悩まされ続けた中でもダーニャという詩集には強烈な郷愁や自己探求というテーマが根底に流れておりおそらくこれは外的世界から隔絶された彼自身の心情そのものだったと言えるだろう
年代初頭になると死神やゴリオ爺さんなど数の記事を書いて世間から注目を浴び始めるその中でも特筆すべきなのは小説貴族だこの作品では貴族階級への批判的視点から描写されておりおそらくこの作品によって現代ロシア文学へ大きな影響を与えただろうただしこの頃になっても社会との摩擦とは無縁ではなく新しい思想潮流との軋轢はいっそう深刻化していった
しかしながら年代初頭まで活動する中で新たなる友人や支援者とも出会い続け大胆不敵とも言える発想力で新作を書き続けたしかしこの創造的活動とは裏腹に私生活では次第に精神的疲労感と疎外感を抱えていたその象徴として年月日の日記には孤独を強調するような記述さえ残しているこうした状況下でもなお様な演劇活動や社交界への参加など自分自身を表現する試みだけには余念なく追求し続けた
そして年月日不運にも彼は軍事訓練中不幸にも命を落としてしまうその死因についてはいまだ議論されている部分も多いそれにも関わらず多くの場合天才肌と称賛された若者であったため周囲から惜しまれつつ葬送された一方その死後わずか数十年経過した今日でもなお新しい世代による再評価がおこない続けておりあるファン曰く今でも身近で共鳴できるよう感じさせます