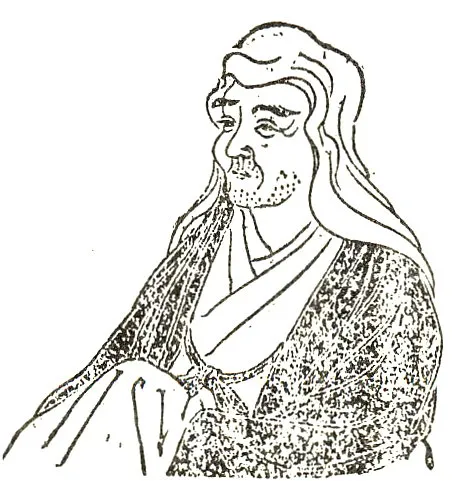
生誕: 1625年(寛永元年12月11日)に生まれる。
職業: 歌人及び俳人である。
没年: 1705年に亡くなる。
影響: 日本の詩と俳句の発展に寄与した。
年寛永元年月日 北村季吟歌人俳人 年
北村季吟年の冬雪が静かに舞う中で生まれた彼はまさに日本の詩の世界に新風を吹き込む運命を背負っていたしかしその道は決して平坦ではなかった若いころから文学への興味を抱き和歌や俳句の魅力に惹かれていったものの当時の社会情勢は彼にとって厳しいものであった季吟はその後自らの文才を磨くために様な師匠から教えを受けたことだろうしかしそれにもかかわらず彼は孤独な戦いを強いられた友人や仲間が次と去っていく中で詩作りへの情熱だけが彼を支えていたと言われているこのような背景からおそらく彼の作品には深い哀愁や孤独感が漂っているのだ年代には名声が高まり始めるそれでもなお皮肉なことに時代は変わりゆきその波に翻弄される日が続いたシンプルさと深みという二つの相反する要素が同居する作品群は多くの読者から支持されたものだそしてこの頃にはすでに俳句という短詩形態も認知されており彼もまたその流派へ足を踏み入れることになった記録によれば季吟は俳句界でも特別な存在として君臨したしかしそれにも関わらず彼の日常生活には悩みや苦しみが常につきまとっていたその内面世界こそが後年多くの作品へ反映されたとも言える例えば古池や蛙飛び込む水音という有名な句にはおそらく自身の日常生活から感じ取った瞬間的な感情が凝縮されていると思われるこの短い表現にもかかわらずその背後には広大な宇宙観と自然との一体感が見え隠れしているまた一部では議論になるかもしれないが季吟自身もある意味で自然との対話者だったとも考えられる多忙ながらも自然との共存について思索し続けた結果多彩で豊かな表現力を身につけていったそしてそれこそが日本文学史上重要視される所以なのだろう年日本人として初めてこの世を去る運命となりその死によって詩壇は大きな空白となったこの事実自体にも皮肉さがありますねその影響力と功績にも関わらず多くの場合人の日常生活から忘れ去られてしまう現在でも北村季吟と名乗る者はいないしかしその遺産はいまだ色あせず人の日常会話や文化的表現として息づいていると言えるそして現代ではなど新しいメディアによって一層多様化した表現方法を見ることになる俳句の形式自体はいまだ人気であり新たなる言語遊戯として広まり続けています今日でも北村季吟によって開花した文学的伝統のおかげで多くの日常風景や瞬間的感覚を捉えようとする試みがありますそれこそ正しく言葉を通じて今この瞬間まで連綿と続いている証拠なのです

