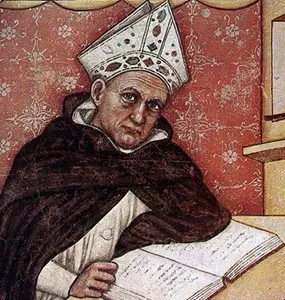生年: 1571年
没年: 1630年
職業: 天文学者、数学者
業績: ケプラーの法則の発表
年 ヨハネス・ケプラー天文学者数学者 年
世紀初頭神秘的な星が夜空に輝く中ヨハネス・ケプラーは地球から約キロメートル離れたウィーンで新たな宇宙の法則を見出そうとしていた年ドイツのシュトゥットガルトに生まれた彼はその時代の天文学と占星術を学びながら成長したしかし彼の心には常に宇宙はどのように機能しているのかという問いが渦巻いていたこれはただの好奇心ではなく彼自身が抱えていた信仰と科学への深い思索でもあった
彼は若い頃から数学と天文学に傾倒しその後年には宇宙の神秘という著作を発表この作品では惑星運動についての理論を初めて提示したしかしそれにもかかわらず当時支配的だったアリストテレス的な世界観と対立し多くの批判を受けることとなった皮肉なことにこの圧力こそが彼をさらに探求へと駆り立てる要因となった
年代初頭になるとケプラーは大著作新しい天文学を執筆し始めるこの作品では自身が発見した三つの法則すなわち惑星運動に関する法則を詳細に記述その中で最も有名なのは楕円軌道でありこの考え方によって彼は太陽系内で惑星がどのように動くかという理解を一変させたある歴史家によればこの発見こそがニュートンによる万有引力説へ至る架け橋となったと言われている
しかし彼の日常生活は決して順風満帆ではなかったケプラーには多くの私生活上の苦悩も存在したそれにもかかわらず新しい理論やアイデアへの探求心は衰えることなく続き人類史上最も重要な科学者たちとの交流や議論も重ねていったそれでも多くの場合資金不足や支持者不在という現実が邪魔をする結果となりおそらくこれが彼自身にも重圧となっていたのであろう
年代にはついにケプラー自身が帝国天文台長官として任命され自身の理論を検証するためには最適な環境であったしかしそれでもなお病気や貧困問題から逃れることはできず特に年その死去前年まで厳しい生活状況が続いていたと言われているこのような逆境にもかかわらず新しい星座や天体観測など多岐にわたり成果を上げ続けた
そして年不運にもヨハネス・ケプラーは生涯歳で世を去るその死後も多く人から称賛され近代天文学の父として知られるようになるしかし皮肉なことにその業績はいっそう評価される一方で生前にはほとんど注目されない存在だったとも言われているおそらくこの不遇さこそ科学とは何かという根本的問いについて考えさせられる要因になっているのであろう
今日でも多くの日常的概念特に物理学や数学 においてケプラー無視できない影響力を持つ人物として広まり続けていますまたその遺産とも言える科学的手法は現代科学研究にも色濃い影響がありますあるファン曰くもしも彼が今生きていたならばおそらくで自説をごまんじょうする姿を見ることになっていただろうと語っていますその業績と精神性こそ一部現代人には依然として魅力的なのです