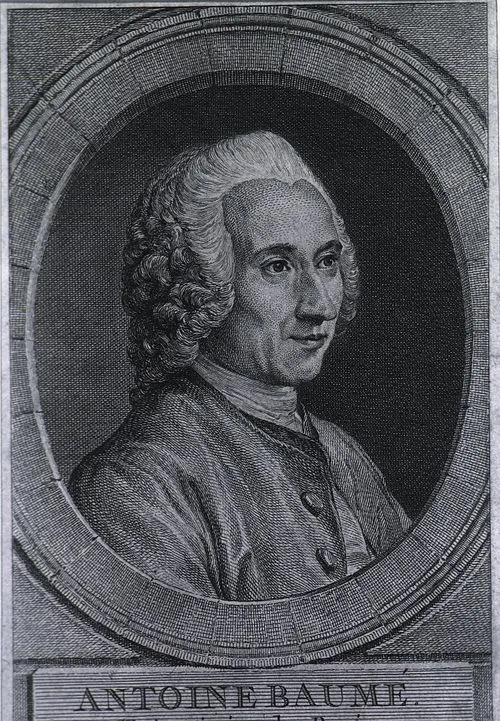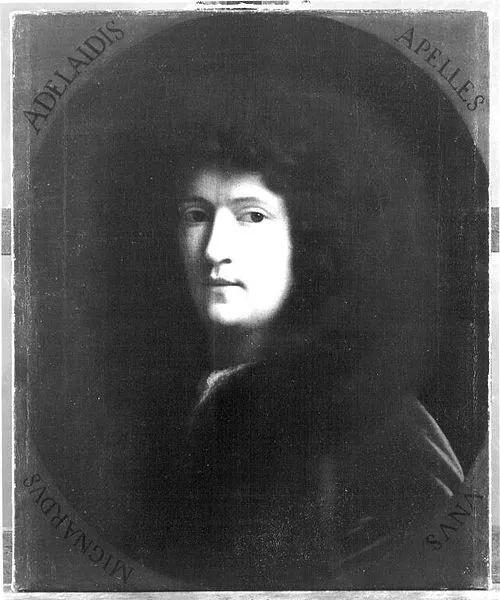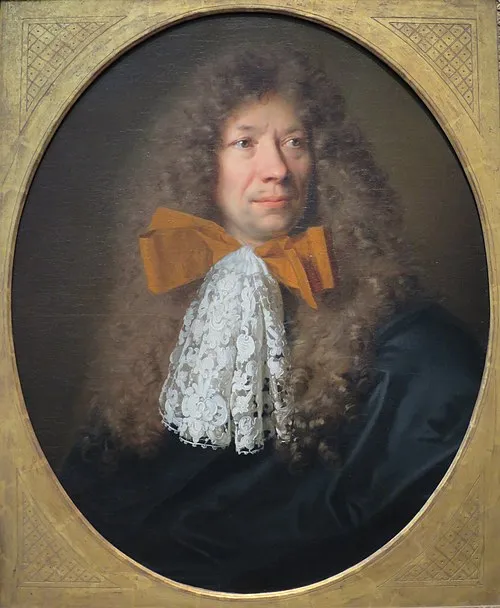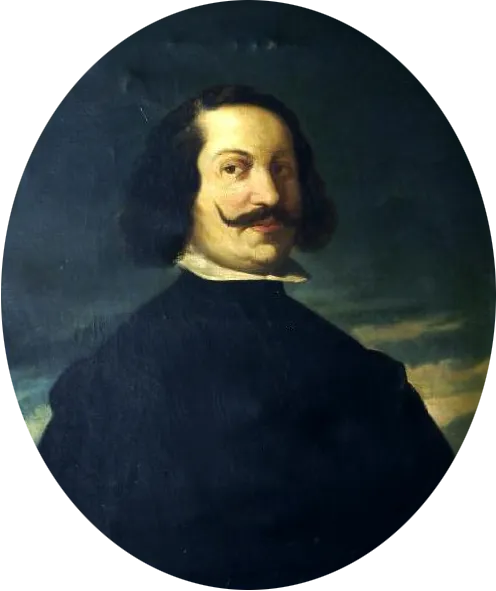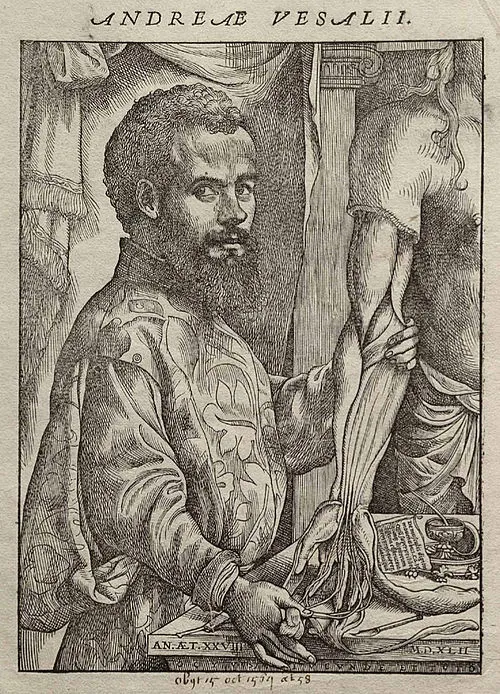生年: 1784年
死年: 1817年
職業: 東洋学者
国籍: スイス
年 ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルト東洋学者 年
彼がこの世に誕生したのは年のスイスのチューリッヒ生まれた時から彼には特別な運命が待ち受けていた両親は彼に豊かな教育を施し彼はその後ヨーロッパの知識人たちと同じく古典や哲学に傾倒するしかしその知識欲は単なる教養を超え異国文化への探求心へと変わっていった年ブルクハルトはある大きな決断を下すそれはアラビア半島への旅だったこの地への冒険心から発せられた選択であり自身がどんな試練に直面するか想像もつかなかっただろうしかし旅立つ前夜不安と期待が入り混じる心境だったと思われる東洋の神秘的な文化や歴史に触れることになるとはしかしこの旅路は容易ではなかった砂漠を越え多くの困難と直面したブルクハルト中でも人との交流が大きな試練となったことだろう一見冷淡で無関心そうに見える異国の人とのコミュニケーションには苦労しながらもおそらく彼は少しずつその土地になじみその文化を理解する術を学んでいったそして何よりも皮肉なのは彼自身が持っていたヨーロッパ的視点によってさまざまな偏見や先入観が芽生えてしまったことだブルクハルトの功績と言えばその洞察力と観察力によるものである最初期の東洋研究者として多くの地域や文化について詳細な記録を書き残したまたそれだけでなく政治的・社会的背景にも言及しながら彼自身の考えを明確化していったそのため古代文明の研究にも寄与したと言えるだろうしかし一方で当時流行していた植民地主義的視点にも影響されてしまった部分もあるそれゆえ非西洋文化への認識について議論が巻き起こることもしばしばだったという意見も存在する果たしてそれが彼自身によるものなのかそれとも当時の社会背景から来ているものなのかまたブルクハルトと同時代人たちとの違いについて考えてみても興味深い例えば他国へ移り住んだ研究者達はその地で生活しながら現地民との接触を重ね自身もそのコミュニティー内に溶け込む道筋を選んでいたしかしブルクハルトの場合あくまで観察者としてその地を見ることに重きを置いていたようにも思えるこの姿勢こそがおそらく後世へ残すべき貴重な資料となり得た一因でもあった年にはレバント地方現在のシリア・レバノン辺りへ足を運びアラビア旅行記を執筆この作品では数多くの重要事項や出来事について描写されておりその内容はいまだなお価値ある情報源として評価され続けているただここでもまた皮肉なのはこの著作活動自体が進行中という不完全さゆえ新しい知見や誤解も含まれているということであるさて年にはエジプトへの旅行計画を立てるもののおそらく健康上の理由から実現せずそれでも彼の日探求した成果物群はいずれ歴史学や東洋学界において高く評価され続けるその影響力はいまだ衰えるところ知らず現代でも多様性や異文化理解への重要性というテーマにつながっているようにも感じ取れるしかし悲劇とも言える結末は年この年自宅近郊で息絶えてしまうしかし何故かその死後数十年経過して初めて名声が広まり始め多くの場合評価されない命掛けの日それ自体特有だったからではないだろうか今日でもブルクハルト名義の記事や書籍を見る機会がありますそしてその影響力 皮肉にも今なお世界各国で議論されていますあまり知られていないスイス出身者であるとは誰も気付いていないほど多岐にわたり研究成果物群のみならず異国に対する魅力不思議さまで引き起こしています晩年まで探求心旺盛だった姿勢それぞれ異なる視点から見ることで新しい光景へ導いてほしいと思わせますそして過去年以上経過した今だからこそ尚更大切になっているテーマです異なる意見・立場を尊重する上で何より必要不可欠となります最後になりましたが現在世間一般では遥か昔信じ難かった思想・価値観など本当に当たり前でしょう そんな中自己犠牲と化して長旅乗り越え努力された結果など感謝しかありません 今回伝われば幸甚です