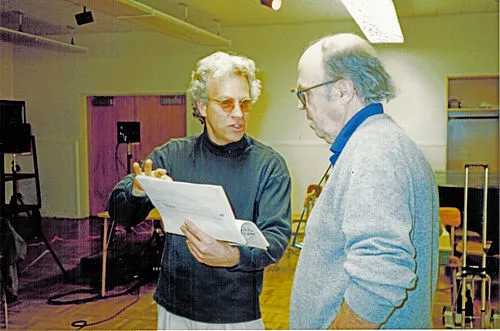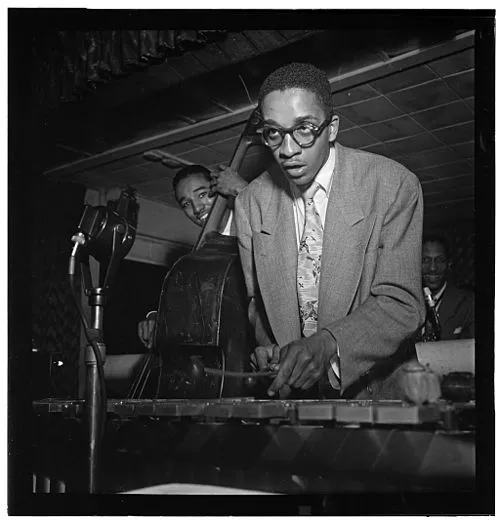名前: 日比野丈夫
職業: 歴史学者
生年: 1914年
没年: 2007年
日比野丈夫歴史学者の軌跡
年東京で生まれた彼は戦争と平和が交錯する な時代の中で育った若き日比野は文化的な背景を持つ家庭に恵まれその影響からか早くから歴史に対する強い興味を抱いていたしかし太平洋戦争の勃発によって多くの日本人が困難な状況に直面する中彼はその好奇心を学問へと昇華させる道を選ぶ
大学では歴史学を専攻し特に古代日本史への関心が深まった卒業後すぐに教職につきその情熱は学生たちにも伝染していったしかしそれにもかかわらず日本の戦後復興期には多くの教員たちが新しい価値観との葛藤に悩むことになる日比野もその一人であり新しい時代を受け入れるためには自らの視点をどう変えるべきか考え続けた
年代に入ると彼は研究者として注目され始めた当時日本国内では社会的・政治的な変動が起こり多くの若者が新しい思想や歴史認識を求めていた皮肉なことにこのような混乱した状況こそが日比野には新たなインスピレーションとなったのであるそれゆえ彼は自身の著作や講義を通じて日本文化や歴史について独自の視点から解説することで多くの支持を集めることになる
おそらく彼の最大なる貢献は古代日本文化論における独自理論だろう彼はそれまで主流だった見解とは異なる視点から古代文明への理解を深めようと試みその過程で数多くの記事や書籍を書いたこの努力によって多くの読者へ影響を与えただけでなく新世代の研究者達にも大きな刺激となった
不屈の日比野学び続ける姿勢
年代には自身が立ち上げた現代日本思想研究所を拠点としてさらなる活動へと移行していったこの機関では日本だけでなく国際的な視点からも歴史や思想について議論され多様性あふれる意見交換が行われていたしかしそれにもかかわらず一部では保守派との対立も生じこの対立は徐に激化していった
このような環境下でも日比野自身は決して折れることなく自身信じる道へ進んだそしてその姿勢こそが真摯さと誠実さという形で広まり多くの人から尊敬され続けているまたこの時期の日比野によって設立された研究機関はいまだ活発に活動しており新世代への教育プログラムなども展開されているという
晩年の日
年月日長い研究生活に終止符が打たれたそれまでの日常には数え切れないほど多くのみんなとの出会いや知識共有それらすべてがおそらく人生そのものだったと言えるだろうしかしながら自分自身より大きいもののためになりたいという思いや社会貢献への欲求は死後も続いているもし今生き返ればどんな未来を見るだろうかそう想像せずにはいられないほど充実した人生だったと思える
遺産として残したもの
現代になってなおその存在感は色褪せない日比野丈夫氏その名声はいまだ教育界・学術界だけではなく広範囲へ及んでいるまた今日でも多様性豊かな地域社会形成への貢献として多岐わたり評価され続けているただ単純ないわゆる教授と呼ばれる存在以上知識欲求旺盛な探求者として多角的視座のお手本とも言える存在だったとも言える
やオンライン講座など媒体も増えてきつつある中今でも通用するの言葉通りオンライン上でも彼のお話し方・考察スタイル等再評価され始めている一方本業以外でも地元高校訪問など積極的参加した事例もうわさされていますそれゆえ地域住民との結び付きもさらに強化されたとも言われています改めてもしかするとこれこそ最期まで残したメッセージなのかもしれません学び続けよ
そして今
私達一人一人にも責任がありますこのフレーズおそらく現在生き残り活動し続ける他分野有名人含むアカデミック領域共通テーマだと言えるでしょうその追憶せん限り未来図式描かなければならぬ事実そこには必要不可欠存在として思案重ねたい部分あれば尚更良し果たして日比野氏故郷目指し何度行脚されたのでしょう未明家族裏話含む密接取材想像すると共感覚得ずには居られませんでした