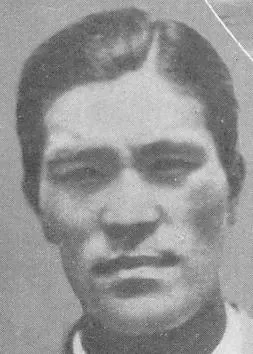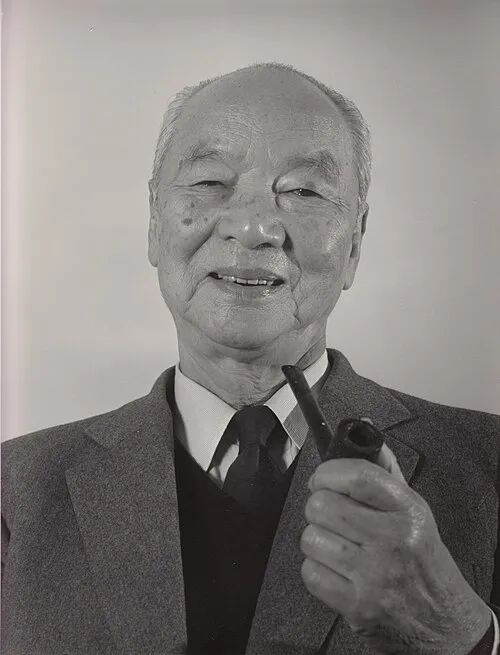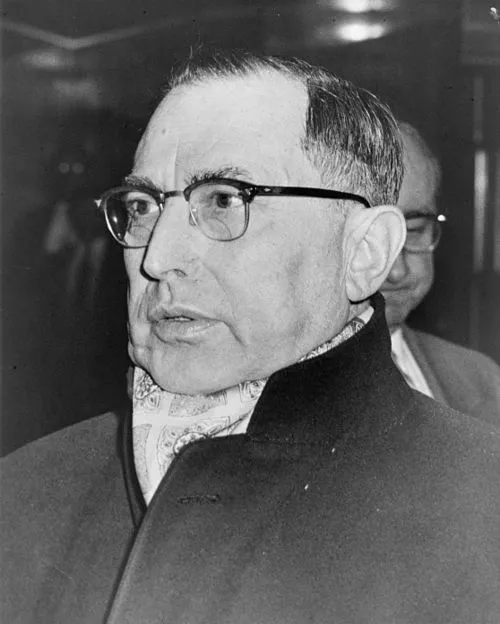生年: 1905年
名前: 円地文子
職業: 小説家
没年: 1986年
円地文子日本文学の新たな風をもたらした小説家
年彼女は静岡県に生まれた彼女の幼少期は明治から大正へと変わる激動の時代に位置しその環境が後の作家人生に大きな影響を与えたことは間違いないしかし円地文子はただの作家ではなかった彼女は言葉を武器にし自身の内面的葛藤を作品で表現することによって多くの読者に共感を呼び起こしたのである
青年期文学への興味が芽生え始めるとともに彼女は多くの古典作品や現代文学に触れその影響を受けていったそれにもかかわらず自分自身の独自性を追求する姿勢が強かったため最初は思うような表現ができず悩んだというしかしそれらの日が後彼女を支える土台となった
年代になると彼女はいよいよ自らの声として短編小説を書き始める代表作となる山椒魚など多くの作品が登場しその中で描かれる人間模様や社会問題について深い洞察力が見せつけられたこの頃から日本文学界でも次第にその名声が広まりつつあったしかし同時期日本全体が戦争へと向かう中で人の日常生活や精神的苦痛も描写されていたため彼女自身も苦悩することになった
皮肉なことに戦争という非常時にも関わらず母なるものとして描かれる女性像や家庭内で繰り広げられるドラマには新しい価値観が反映されていたこのような視点から見るとおそらく円地文子自身も戦争によって失われてしまう日常生活への懐古感から創作意欲を刺激された部分もあっただろう
戦後復興と新しい文学運動
戦後日本全体は再建へ向けて動き出すその波にはもちろん円地文子も乗っていた年には椿姫において新たな試みとして原作とは異なる視点から物語を紡ぎ出すことで注目されたこの作品では従来とは異なる女性像自立した女性を描写することで多くの読者から共感と支持を得る一方このような革新的アプローチには賛否両論あったもののそれでもなおこの挑戦的姿勢こそが彼女自身だった
晩年と影響
その後も執筆活動は続き小説だけでなくエッセイや評論でも存在感を示していったしかしながら高齢になり身体的衰えも見えてきた頃自身のお気に入りだった静岡県内で過ごす時間が増えていくそれにもかかわらず生涯現役として執筆し続け日本文学誌上などでもその意見・考え方を発信し続けた果敢さゆえか一部ファンから不屈の象徴とも呼ばれる存在となっていた
遺産として残されたもの
年生涯年以上書き続けた円地文子はこの世を去るその死去後多くの記事や著書では改めて日本女性作家という位置づけ以上に人間・円地文子という存在について考察されているそして今日まで彼女への評価は高まり続けまた一人新しい風格などと言われるまでになった皮肉なのだろうか亡くなる数年前には全国的規模で開催された座談会などにも参加しておりそのエネルギーはいまだ衰えるどころか周囲へ伝播していた様子だ
現代との接点
今なお日本文学界ではその功績が色濃く残りその創造性や多様性について議論され続けている私の日記と称したエッセイ集には今でも触発される若手作家達がおり一種ルネサンスとも言える流れさえ感じさせるその意味ではおそらく経済成長や国際化という大波によって逆境にも直面した近年だからこそ高橋松太郎氏との合作によって生まれたいわゆる逆境小説が脚光浴びてもいるのであるつまり本質的には歴史的人物との繋ぎ合わさりますね
(2019年現在)読み返してみれば歴史深淵とも言える魅力満載と言われますこのような形で継承され続け特定ジャンルだけじゃなく多方面で取り扱われますます若者達へのアプローチ効果加速化していますので良好作品数多いコンクール入選多数等がありますねもし機会あればこの素晴らしい国民文化財とも言える人物をご一緒出来れば嬉しく思います