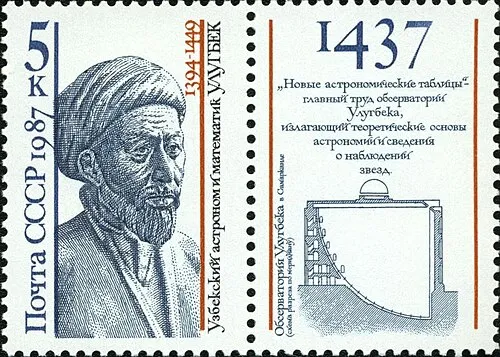名前: アクバル
生年: 1542年
没年: 1605年
役職: ムガル帝国の第3代君主
在位期間: 1556年から1605年
業績: 宗教的寛容の推進と統治の中央集権化
アクバルムガル帝国の偉大な君主
彼の名はインドの歴史において光り輝く存在として知られている年アクバルは帝国の首都であるファテープル・シクリに誕生した王位継承者として生まれたがその人生は決して平坦ではなかった彼が幼少期を過ごす中で父親ホムが死去し彼はまだ若い少年であったため自らの立場を確立することに苦労したしかしアクバルは運命を切り拓く力を持っていた
年彼はついに権力を手中に収めるその後すぐに数の戦争と同盟によって領土を拡大し始めたこの時期アクバルには特異な才能があったそれは彼自身が実行した政策や改革によって人から支持されることだったしかしその成功には陰もあった教会と同盟を結んだもののこの決断は貴族たちの怒りを買った
皮肉なことに多くの敵対勢力がアクバルの強大さと魅力的なカリスマ性に恐れおののいたおそらく彼が抱えていた最大の課題は多様な宗教や文化的背景を持つ人との共存だったヒンドゥー教徒やイスラム教徒との緊張関係それにもかかわらずアクバルは宗教的寛容さを促進する道を選びディーニ・イラーヒー神聖宗教という新たな信仰体系まで創造したこの試みについて議論する歴史家もいるがそれでも多くの場合この政策こそがムガル帝国長期的発展への鍵となったと言われている
年には一連の行政改革と税制改革も実施されたその結果として新しい財源確保方法や官僚制度強化など多くの場合で経済状況改善へ寄与したしかしながら一部貴族層から反発も受けることになり不安定要因となった特筆すべき点として彼女自身一族との血縁関係にも目配せしていた点だろう特にビハール王国との結婚協約など
戦争と外交アクバル時代
アクバルによる軍事戦略それこそこの君主特有でありそれまでインド亜大陸では類似例を見ることのできない規模だった年にはパニーパット近郊で行われた戦闘によって根本的勝利しその後コーカス地方への侵攻及びデカン高原へ進出する機会も得るしかしこの拡張主義政策には反響もあり大名家間では恐怖心や敵対意識が広まりつつあった
文化への影響
またまた皮肉なのだがその圧倒的権力下では文化活動も活性化された他民族交流という意味合いでも壮観だったと言えるその一環として建設されたファテープール・シクリは市民生活そのものを変えるほど重要な意味合いしか持たない都市づくりになったこの都市計画のおかげで商業繁栄のみならず新しい知識や思想までも受け入れる柔軟性へ繋げてしまう一体全体このような斬新さとは何なのか 他者理解への扉でもありそこから新しい文化融合とも言えそうだ
最期の日
しかし時代はいずれ終わりを見るそして年その日が訪れた病気によって静かなる眠りについたただしこの死によってムガル帝国全体などその後急激さ故不安定感増加し続けてしまう要因にも繋げられてしまうそれにもかかわらず彼自身遺産とは決して無視できぬ存在感残している本来ならば永遠なる権威だけど本当に残念ながら崇高理念だけ夢見ただけだったとも言える真実を求め続けても良きことである一方しかし現実世界通じ捨て去る必要ない面白さある筈だから